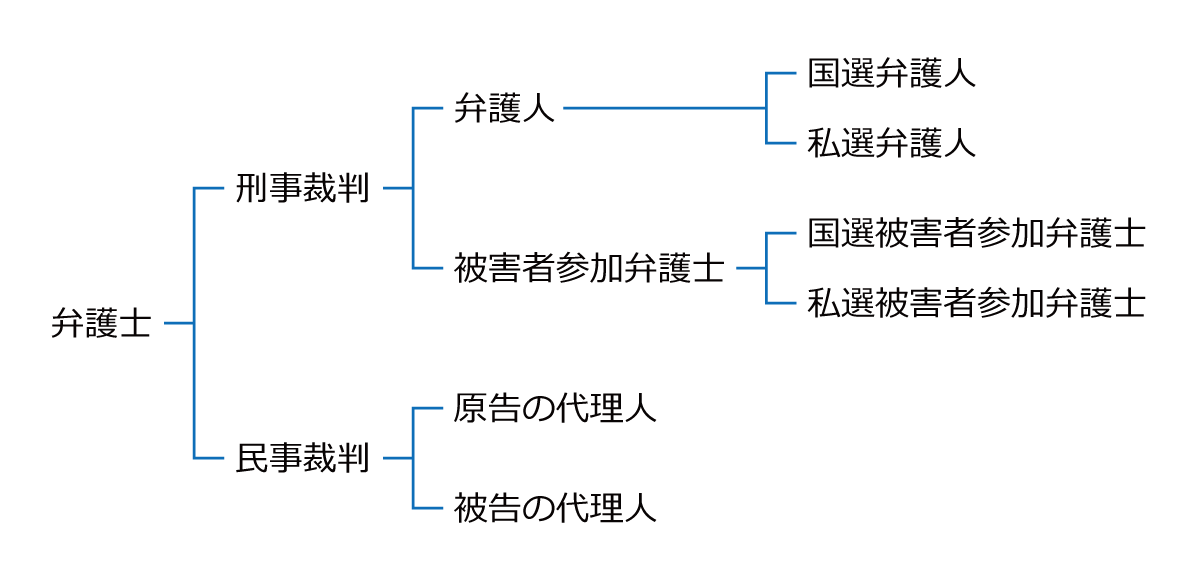質問のカテゴリ
刑事裁判
凶悪犯罪事件・交通事故 共通の質問
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所では、被害者参加制度の創設に深く関わってきましたので、特に犯罪被害者のための刑事裁判(及び後で述べる民事裁判)の支援に力を入れており、数多くの被害者支援の事件をお受けしてきました。
裁判にこれから参加しようかどうか悩んでいる被害者や遺族、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
また、当事務所では、犯罪被害者の支援事件を正式に受任したときは、被害者・遺族の方に少しでも安心していただくため、捜査や裁判の進展によっては、例外的に、通常の営業時間外であっても、対応させていただく場合があります。
【当事務所の方針】
当事務所では、被害者参加制度の創設に深く関わってきましたので、特に犯罪被害者のための刑事裁判(及び後で述べる民事裁判)の支援に力を入れており、数多くの被害者支援の事件をお受けしてきました。
裁判にこれから参加しようかどうか悩んでいる被害者や遺族、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
また、当事務所では、犯罪被害者の支援事件を正式に受任したときは、被害者・遺族の方に少しでも安心していただくため、捜査や裁判の進展によっては、例外的に、通常の営業時間外であっても、対応させていただく場合があります。
凶悪犯罪事件でよくある質問
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所は、死刑制度を積極的に推進する立場です。
また、被害者・遺族の被害の回復と権利の保護を最も大切にし、優先することを方針としております。
弁護士と一緒にタックを組み、検察官と連携しながら、亡くなられた被害者の無念を晴らしたい、名誉を守りたい、適正な処罰を加えて欲しいと思っておられる方、刑事裁判にこれから参加しようかどうか迷っている方、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
⇒ 文藝春秋社「死刑賛成弁護士」
交通事故事件でよくある質問
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所では、交通事故の鑑定人(株式会社日本交通事故調査機構 佐々木尋貴氏)と普段から密接な連携を保ち、協力専門医との連携を常時取るなど、交通工学と医学双方について必要な知識を備えています。
別途費用はかかりますが、現地を調査し、再現実験を実施し、それを検察官に提出することもあります。
その際、理系出身の知識を生かしながら、証拠を科学的に分析し評価することを大切にしております。
また、検察官と連携しながら裁判で被告人と闘う制度である「被害者参加制度」の創設に深く関わってきましたので、検察官とは緊張関係を保ちながらも、しっかりとした信頼関係を築くことを最も大切な方針としております。
さらに、交通事故の遺族団体の代表顧問をしておりますので、遺族団体との連携も大切にしております(一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会「あいの会」)。
交通事故の責任の所在や加害者の責任の程度について、刑事裁判を通して真相を究明し、しっかりと刑事手続きに関わっていきたいと考えている方、あるいは参加しようかどうか迷っている方、(ごく一部ですが)副検事さんの横暴な対応などにお困りの方、あるいは、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は一度、ご相談ください。
報道対応にお困りの方によくある質問
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所では、記者との信頼関係を徐々に築いていくことを基本的なスタンスとしながら、被害者・遺族が報道機関から二次被害を受けないよう、被害者・遺族を守っていきます。
そのため、記者と、被害者・遺族との間のやりとりは、原則として、当事務所を通すようにします。
また、事件直後から、メディアスクラムなど多くの記者が押し寄せてくるような事態が起きたときは、ご自宅までかけつけ、速やかにメディア・報道に対応させていただきます。
一方、個々の記者との間で、個人的な信頼関係を築くことができ、被害者・遺族の方で、「報道を通して自らの思いを社会に発信したい」と希望されるようなときは、そのお手伝いもさせていただくなど、柔軟に対応させて頂きます。
刑事裁判が終わってから
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所では、刑事裁判又は民事裁判を正式に受任した事件の被害者・遺族に対しては、刑事の裁判終了後の受刑者との直接のやりとりについても、相談に応じております。
民事裁判
※質問をクリックすると回答が表示されます。
【当事務所の方針】
当事務所では、交通事故の鑑定人(株式会社日本交通事故調査機構 佐々木尋貴氏)と普段から密接な連携を保ち、協力専門医との連携を常時取るなど、交通工学と医学双方について必要な知識を備えています。
別途費用はかかりますが、現地を調査し、再現実験を実施することも多くあります。
理系出身の知識を生かしながら、証拠を科学的に分析し評価しつつ、できるだけ裁判所に分かり易い書面を書くようにしています。
また、交通事故の遺族団体の代表顧問をしております(一般社団法人 関東交通犯罪遺族の会「あいの会」)。
刑事の裁判がどうしてもおかしいから民事裁判を通して改めて真相を究明し直したい、あるいはどうしようか迷っていて一度、相談してみたい、セカンドオピニオンとして話を聞いてみたいという方は遠慮無くご相談ください。
民事で、改めてどのようなことができるか、一緒に考えていきましょう。